こんにちは。okamotoです。
もうめちゃくちゃ寒いですね。
寒すぎて、一人用鍋を購入し、一人で鍋をしている今日このごろです。
むっちゃどうでもいいですねw
はい!というわけで、
今日は『全は1、1は全』という言葉から「英語のゲシュタルト」について考えてみたいと思います。
「全は1、1は全」
ご存知の方も多いかと思いますが、
この「全は一、一は全」という言葉は「鋼の錬金術師」(以下、ハガレン)というマンガの中で出てくる言葉です。
主人公のエドワード・エルリック(エド)とアルフォンス・エルリック(アル)の兄弟がイズミ・カーティス(後の師匠)に弟子入りする際、
入門試験としてこの『全は1、1は全』という言葉の意味を考えさせるということを課したんですね。
しかも、無人島でサバイバル生活をしながら、です。
なかなか、激しいことをしますよねw
今の時代なら幼児虐待の大問題ですwww
まぁ虐待の話はおいときまして
この『全は1、1は全』という言葉は
マンガの中ではさらっと「全は世界、1は俺(エド)」と答えて終わっていますが、
実は、「錬金術」だけでなく「英語学習」においても大事な考え方なんですね。

結論から言うと、この言葉が表しているのが『ゲシュタルト』という概念になるということです。
ゲシュタルトとは?
小学生の時、漢字練習帳に漢字をたくさん書いていて、
漢字が気持ち悪い形に見えてくることってありましたよね?
あの現象が『ゲシュタルト崩壊』と呼ばれていることはわりと知っている人も多いと思います。
そのゲシュタルトが『全は一、一は全』の言葉であり、英語学習に必須な考え方ということです。
では「ゲシュタルト」とは何か?
ゲシュタルトは『全体と部分が双方向に関係し、全体成しているという概念』のことです。
例えば、テレビにめちゃくちゃ近づいて見てみると「赤と青と黄色の点」が見えます。
子供頃、誰しもがやったことがあるんじゃないでしょうか?
(今のテレビじゃ見えないかも…)
それぞれ光の点は単発の色で、何の意味を持っていません。
しかし、離れて見て見としっかりと映像となっていて、意味を成しています。
『意味を持たない部分が集まり、全体となることで意味を成す』
これを『ゲシュタルトを形成する』と考えるわけです。
もう1つ例を考えてみます。
「魚」という概念は「鮎、マグロ、アジ、鮭」などの種類の魚によって定義されているわけではありません。
そして「魚」という概念があって、それが個々の魚に当てはまるというわけでもありません。
鮭やマグロのようなそれぞれの魚と抽象度の高い「魚」という概念が双方向に関係して初めてそれぞれが成り立っているのです。
だから、見たことのない魚を見ても、ゲシュタルトからそれが魚だとわかるのです。
エルリック兄弟の出した「全は世界、1は俺」という結論のは
世界は自分のような存在がないと成立しないものである一方で、
世界がないと自分というものが存在し得ない。
双方向に関係性が存在して、世界と自分が成り立っている。
ということです。
この考えに、子供で、しかも無人島のサバイバル生活中に気づくというのは、
やっぱりエルリック兄弟は天才ですね!w
英語学習はゲシュタルトを構築すること
では、このゲシュタルトですが、
『言語とどのような関係があるのか?』ということですが。
母国語を学ぶ過程においては、知らず知らずのうちに形成されます。
なんとなく感覚的にわかるかもしれませんね。
例えば、「観察する」「視察する」「監査する」「検査する」「目視する」「目の当たりにする」ような似たような言葉があります。
この言葉の高い抽象度の言葉は何でしょうか?
「見る」ですね。
全部、「見る」という言葉と関係しています。
このように母国語では自然とゲシュタルトの構築が行われ、それらを使いこなす事ができます。
しかし、第二言語として大人が英語を学ぶ過程においては、
意識的にゲシュタルトの広がりを学ぶ必要があります。
実はここが「日本語と英語の対訳学習の悪いところ」でもあります。
日本語には日本語のゲシュタルトが広がっているのと同様に
英語には英語のゲシュタルトが広がっています。
もちろんその広がり方は異なります。
英語を学ぶ時は、英語のゲシュタルトの広がりを意識するのが良いということですね。
はい、今回の内容は以上になります。
何気なくハガレンを読んでいると素通りしがちなセリフですが、
「英語学習にも通ずる、めっちゃええことを言っていた!」というお話です。
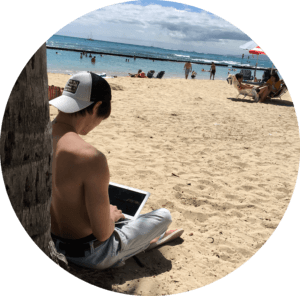
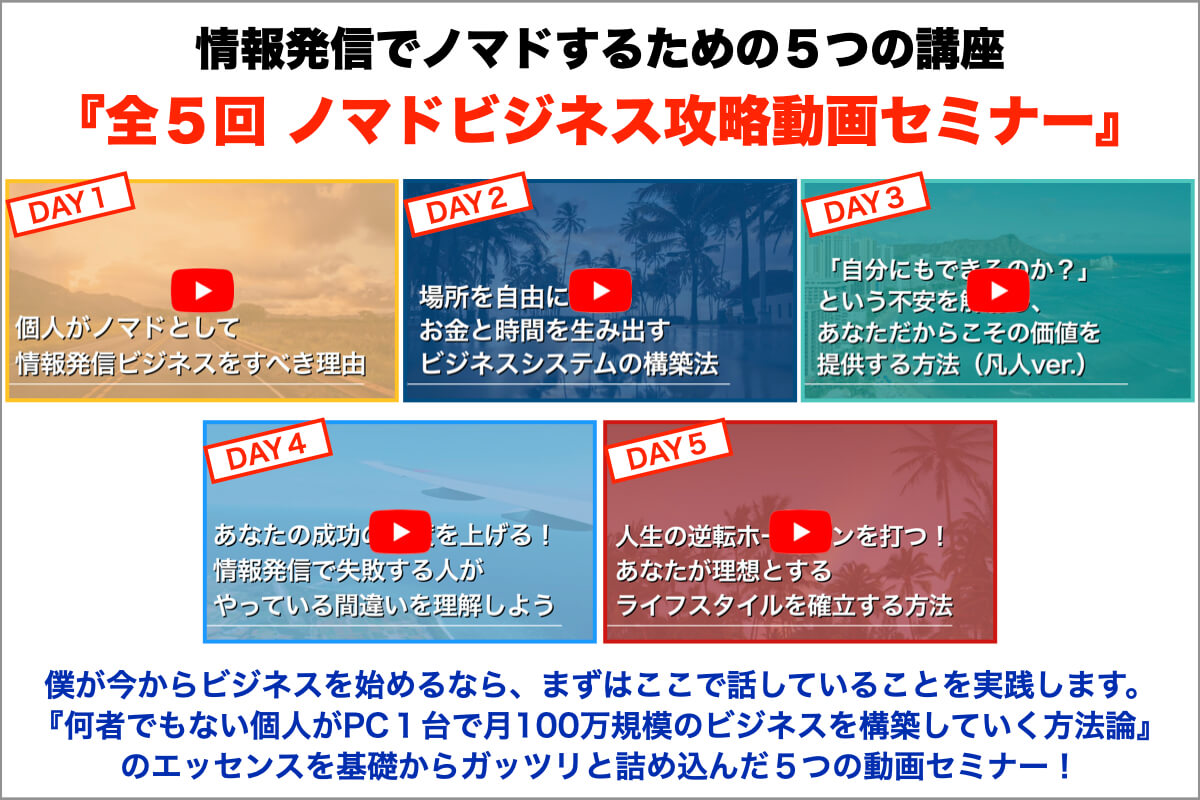
 (↑ こちらをクリック ↑)
(↑ こちらをクリック ↑)